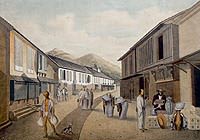第113号【長崎の秋の食卓を彩る魚たち】
代表的な秋の魚といえばサンマ。脂がのったこの時期はやっぱり塩焼きが一番。 あの香ばしい匂い、ホントにたまりません。 そのサンマ以上に魚屋の店頭で目立っているのは、やはり今が旬のサバです。 どれも目が澄み、尾の方までぷっくり太っていておいしそう。 シメサバや味噌煮などいろんなメニューが頭に浮かびます。 (^∇、^)“カマス“もオイシソー▲お店に並んだきれいなサバ サバは青背魚の中でも「頭がよくなる」と話題になった栄養素、 EPAやDHAが多く含まれ、ガンやボケ防止にも効果があるといわれています。 健康のために家族でたくさん食べたいものです。 ちなみにこれから冬にかけて五島沖や対馬海峡などで獲れるサバは、 非常に脂がのっておいしく「旬(とき)サバ」というブランド名で長崎県外に出回っているそうです。あなたの街の魚屋さんで「旬サバ」を見つけたらぜひ味わってみて下さい。 (’▽‘)/ヒト味違ウ美味シサ 「モチ魚(ウオ)」もおいしい季節。関東方面ではイボダイと呼ばれている魚です。 エラの上に黒い斑点を持ち、ちょっと丸みのある姿をしています。甘鯛に似た淡白な味わいです。 関東では「イボダイの開き」はちょっとした高級品らしいのですが、長崎では割合リーズナブル。 ちなみに選りすぐりの塩干品を置いている長崎の某デパートでは、五島沖産モチ魚の一夜干しは2匹で500円でした。 一般家庭では刺身やカラ揚げ、煮付けなどでいただくことが多い魚です。 (^^)肉厚デ、美味!▲五島沖産のモチ魚とカマスの開き 長崎で「アゴ」の名で親しまれている「飛び魚」も旬です。 最盛期(9月下旬~10月上旬)は過ぎましたが平戸周辺で行われているアゴ漁は特に有名で、初秋の風物詩。 山陰沖を季節風にのって南下して来たアゴの群れが飛行機の翼のように胸びれと腹びれを広げて海面上を泳ぎ、 青い身体をキラキラ輝かせる光景が見られるそうです。それを地元の人々が網ですくってとり、焼きアゴ、塩アゴに加工して全国に出荷します。 上品な風味のあるアゴのだしは、長崎のお正月の雑煮や五島うどんに欠かせません。 ところで一年通して新鮮な魚に恵まれている長崎の家庭では、かまぼこを手作りしているところが多いです。 つい先日も我が家ではエソ、サワラが手に入ったのでさっそく作りました。母はすり鉢を使います。 機械混ぜに比べ手間がかかり、夏などは汗だくになるのですが、仕上がりが違うのだそうです。 家庭で作るかまぼこは味や形など家ごとに個性があります。 かまぼこ一切れでその家の味つけの好みやセンスが見えて来るような気がして面白いです。 (^~、^)ンマカ、カンボコばい。▲我が家の手づくりかまぼこ
もっと読む