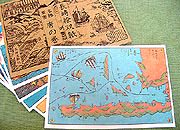第128号【浦上(時津)街道を行く】
長崎市の北隣で、西彼杵半島の付け根に位置する西彼杵(にしそのぎ)郡時津(とぎつ)町。 近年、長崎市のベッドタウンとして成長したこの町は、古くから交通の要所として知られ、 江戸時代は浦上街道(別名、時津街道)の道筋として栄えたところでもあります。 (^ー、^)名物 "時津饅頭" オイシカヨ 江戸時代、海外の文物を求めて全国の商人や文人墨客が往来した長崎街道は、 長崎から東に位置する日見峠を経て、矢上~諫早~大村~松原~彼杵、 そして佐賀県の嬉野、福岡県小倉へと続くルートがよく知られています。 しかしこのルートは時代によっていくつかのコースがあったそうで、 その最も古いコースといわれているのが長崎~時津を結ぶ「浦上街道(別名、時津街道)」です。 長崎から北上し、同市内を浦上、滑石を経て時津に至り、そこの港から大村湾を舟で渡って彼杵へ。 それから嬉野へと辿る「浦上街道」は江戸時代の中頃まで大いに利用されていたそうです。 旅人らが海路へと乗り換える時津港の近くには今も大名が休憩や宿泊に利用したといわれる茶屋跡があります。▲1817年に建造された茶屋の跡1817年に建てられたというその古い家屋は改築・修理がされていますが、 石垣や屋敷の門に当時を偲ぶことができます。 (´ー` )街道筋ラシイ風情デス そこから1kmちょっと長崎市方面へ向かったところに、この街道で一番の名所があります。 それは「継石坊主(ツギイシボウズ)」、別名「鯖腐岩(さばくさらかしいわ)」と呼ばれる奇岩で、 高さ20mはある大きな岩の上に、さらに不安定そうに岩が載っていて、今にも落ちてきそうなのです。 (;° ロ°) オトロシカ~(怖い)▲奇岩、鯖腐岩 江戸時代の文芸作家で狂歌師として名を馳せた、太田蜀山人(太田南畝)が、 長崎奉行所の役人として在勤していた時、 この奇岩を見て「岩かどに立ちぬる石を見つつをれば になへる魚もさはくちぬべし」と、 落ちてきそうな岩を怖がり、 とうとう鯖を腐らせたという意味の歌を詠ったのが「鯖腐岩」という名の由来だそうです。 ( ’.’)今モ当時ノママ この奇岩を眺め通った後、旅人らはこの街道最大の難所と呼ばれた「打坂峠」を越えなければなりませんでした。 現在は国道が通り、当時の様子は分かりませんが、起伏が激しい峠道だったようです。 そこを抜けるといよいよ滑石、浦上と長崎の市街地へ入ることになります。 ところでこの街道は1597年に、 豊臣秀吉のキリスト教禁止令によって西坂の丘で殉教した「日本二十六聖人」たちが通ったことでも知られています。 京都や大阪で捕らえられた彼らは、長崎で処刑される前夜、 彼杵から大村湾を横断して時津へ着き、舟中で一夜を過ごしています。 浦上街道は彼らの聖なる足跡を残した最後の道だったのです。 (・_・、) 悲シクモ感動的ナ聖人タチデシタ▲「日本ニ十六聖人上陸の地」の碑
もっと読む