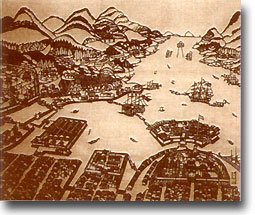第523号【明治・大正の面影残る長崎公園】
今年も「ながさき紫陽花まつり」(5/20〜6/11)がはじまりました。出島やグラバー園、眼鏡橋、シーボルト記念館などで、咲きはじめの初々しい紫陽花が市民や観光客をお出迎え。紫陽花の花色は「七変化」の異名のとおり、日毎に表情を変えながら人々の目を楽しませています。 雨の季節がはじまる前に、新緑を楽しもうと長崎公園(長崎市上西山町)へ行ってきました。長崎の市街地を見渡す丘稜地にあり、諏訪神社に隣接する長崎公園は、明治6(1873)年に太政官布告により制定された長崎でもっとも古い公園です。 そんな由緒ある公園だからか、園内には明治・大正時代のものが点在。そのひとつが、池に設置された装飾噴水です。これは、明治11年(1878)頃に造られた日本最古の装飾噴水だそう。ふだんは高く吹き出る水にばかり目が行きますが、噴水のデザインをよくよく見ると、モダンで美しい。ハイカラ好みの明治の名残でしょうか。また、池のそばで営業している月見茶屋は、明治18(1885)年創業。名物のぼた餅は、甘さ控えめの変わらぬおいしさでありました。 長崎公園は、長崎の歴史を物語る数々の顕彰碑や文学碑があることでも知られています。そのなかのひとつ「郷土先賢紀碑」は、いまから100年前の大正5年(1916)に建立されたもの。碑には海外貿易、医学、国文学、儒学、砲術、活版術、写真術、慈善などさまざまな分野で功績を残した日本人79人、外国人22人、合計101人の名が刻まれています。 漢字の古い書体のひとつである篆書体(てんしょたい)で刻まれた碑の題字「郷土先賢紀碑」は、徳川宗家16代目の徳川家達(1863〜1940)の書。家達は明治維新後、公爵を授けられ貴族院議長を勤めました。また、外国人の名はカタカナと合わせて洋字(ローマ字)でも刻まれているのですが、洋字は、長崎学の礎を築いた古賀十二郎(1879〜1954)によるものです。 「郷土先賢紀碑」を建立したのは、「長崎市小学校職員会」。郷土の先賢を後世に伝え、将来を担う子供たちの励ましにするのが目的だったよう。それにしても、なぜ、家達が題字を書くことになったのか。碑の近くには徳川家ゆかりの東照宮(安禅寺跡)があるのですが、何か関係があるのでしょうか。ちなみに、洋字を書いた古賀十二郎の記念碑は、公園そばの長崎県立図書館前に設けられています。 「郷土先賢紀碑」のある広場の片隅で、アメリカ合衆国大統領ゆかりのアコウの木が葉を生い茂らせていました。明治12年(1879)6月、第12代アメリカ合衆国大統領の任期(1869〜1877)を終えたグラント将軍が、軍艦で世界旅行の途中、長崎に寄港。5日間ほど滞在し、長崎公園で開催されていた長崎博覧会を視察するなどしました。アコウの木はその際にグランド将軍夫妻が記念に植樹したものです。日本側は夫妻を国賓待遇で迎え、迎陽亭で歓迎会を催しています。 歴史家たちは、グラント将軍を軍人としては高く評価していますが、大統領としては残念ながら真逆で、スキャンダルや汚職により、最悪の大統領のひとりともいわれているそうです。時はめぐり、いまは第45代アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプ氏の時代。はてさて、後世の人々はどんな評価をするのでしょう。
もっと読む