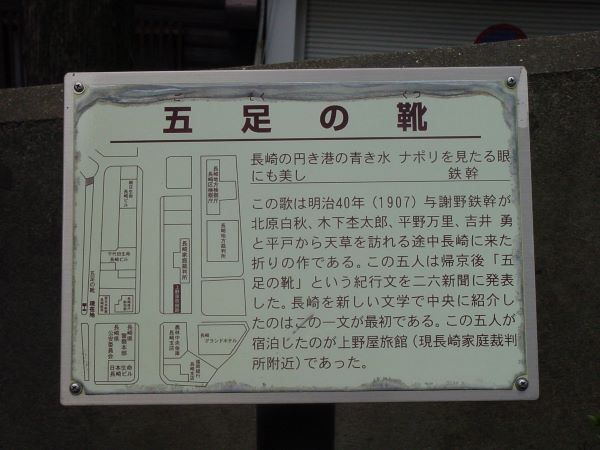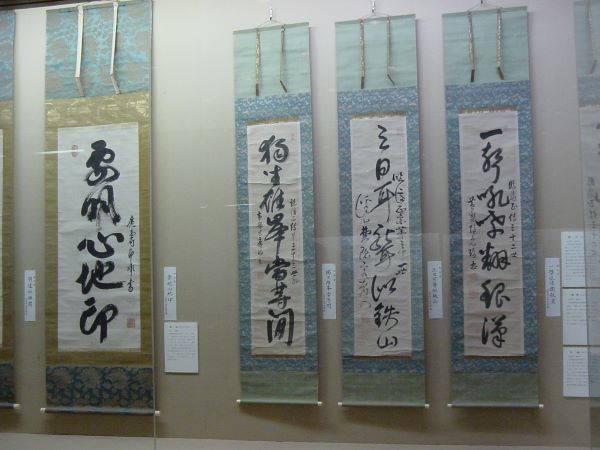第233号【焼きものの里、三川内皿山を訪ねて】
佐世保駅から東へ車で約25分。緑豊かな山あいののどかな風情が漂う佐世保市三川内。ここは、かつて肥前・平戸藩の御用窯として発達した歴史ある焼きものの里。今もたくさんの窯元が「三川内焼」400年の伝統を受け継いで創作活動を続けています。 佐賀県との県境にもほど近い三川内の周辺には、全国的に有名な有田焼(佐賀県有田町)や波佐見焼(長崎県波佐見町)など、古くからの窯業地が点在しています。江戸時代に肥前と呼ばれたこれらの地域で焼かれた磁器は、有田から北に十数キロ離れた伊万里港に集められ、船で各地に運ばれていました。その磁器たちが、消費地では、積み出された港の名前から伊万里焼と呼ばれていたことはよく知られています。 三川内焼は、約400年前、豊臣秀吉が起こした朝鮮の役の際、連れ帰った朝鮮の陶工に、26代平戸藩主の松浦鎮信(まつら しげのぶ)が平戸で焼かせたのがはじまりです。藩主の命を受けた巨関(きょかん)という陶工は当初、平戸の中野のという所に窯を築いて焼いていましたが、よりよい陶石を求めて平戸領内を探索し、最終的に藩領の南端に位置する三川内に落ち着いたのでした。 その後、藩窯として整備されていったこの地には、木原山、江永山、三川内山の3つの皿山(※陶磁器が焼かれる窯場一帯のこと)があります。いずれも人目を避けるかのように小さな山に隔てられた地形の中に窯元があります。「当時、焼きものの技術は秘法で、藩外へ流出しないよう厳重に取り締まられました。奥まったところにある三川内は地理的にも適していたのでしょう」と地元の方が教えてくれました。また、三川内焼の特長について、「天草の陶石を調合して生まれる純白の白磁に、呉須による繊細な染め付けが真髄。本当に飽きのこない美しさなんですよ」とのこと。それは当時、朝廷や将軍家にも献上されるほどの繊細優美な白磁でした。 三川内焼で代表的な絵柄として知られているのが「唐子絵」です。唐子が戯れる構図は、今でこそお馴染みですが、江戸時代は「お止め焼き」と言って平戸藩窯でしか焼くことを許されず、幕府や諸大名への贈答品として使われていました。 また三川内焼は、茶道具としても発達しました。29代平戸藩主で茶道・鎮信流の流祖でもある松浦鎮信(まつら ちんしん)は、この地に藩窯を整えた人物で、多くの精巧優雅な名品をつくらせています。優れた焼きものづくりへの情熱は、陶工たちの技を高め、透かし彫りやひねり物、細工物といった多様な技法を生み出していきました。当時の貴重な作品は、「三川内焼美術館」(※JR三川内駅近く)で見ることができます。 三川内では窯元めぐりも楽しみのひとつです。先祖が平戸藩御用窯の創立時に多大な貢献をしたという「平戸洸祥窯」で、ユニークな作品に出会いました。八画面という珍しい形をしたちゃんぽん専用の白磁の丼です。「具材が映え、食べやすい形をめざして創りました」という17代目の中里一郎氏。伝統を大切にしながら新たな焼きものづくりへ意欲を燃やす現代の三川内焼の陶工の姿がそこにありました。◎平成17年5月1~5日「三川内焼はまぜん祭り」。三川内皿山にて開催。◎ 取材協力:平戸洸祥窯、三川内美術館◎ 参考にした資料や本/三川内焼窯元巡り~皿山三味(佐世保市)
もっと読む