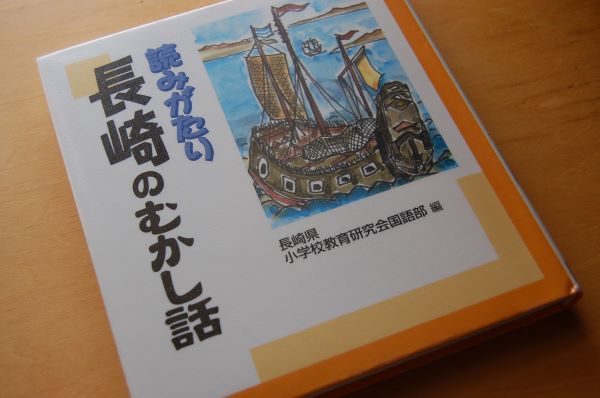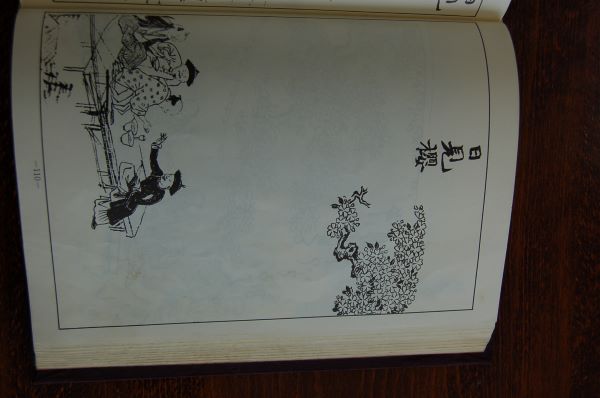第341号【茂木くんちに、行ってきました】
秋祭りのシーズンです。長崎では、10月7、8、9の「長崎くんち」が終わると、約1カ月間に渡って、「郷(さと)くんち」とよばれる祭りが市内各地で行われています。たとえば、竹ン芸が奉納される「若宮くんち」、獅子浮立が行われる「矢上くんち」、女相撲で知られる「式見くんち」など、その地域の歴史・風土を物語る伝統が残されていて、その数は確認されているだけでも30数カ所はあるといわれています。 つい先日、長崎市茂木地区の「茂木くんち」へ行ってきました。長崎駅から車で約20分。市街地から緑の山を越えたところにある茂木地区は美しい橘湾に面した地域で、古くから漁業が盛ん。長崎市内でもとくに魚のおいしいところとして知られています。茂木の港は、江戸時代には鹿児島や熊本方面へ通じる交通の要衝でした。また、明治時代には長崎の居留地に住む外国人の避暑地としても栄えるなど、たいへん個性的な歴史を持つ土地柄です。 「茂木くんち」は茂木地区の総鎮守である裳着神社(もぎじんじゃ)の祭礼です。長崎市内でもっとも古い神社といわれ、「裳着」の名は、日本書紀に登場する神功皇后が三韓出兵のときにこの地に立ち寄り、裳(衣装)を着けたことに由来するそうです。 「茂木くんち」は毎年10月中旬の土日(2日間)に行われています。以前は、決まった日にちがあったそうですが、平日だと人の集まりが悪くなるため、いまのように変わったそうです。私たちが訪れたのは2日目で、裳着神社でお参りをした後、沿道にくだって「お上り」の行列を見物しました。 行列の先頭を歩いてきたのは、5メートルほどはありそうな長い鉾(ほこ)を持った男性です。着流しに赤いズボン、草履という、どこか南方系を思わせる個性的な出で立ちです。ときどき立ち止まっては、長い棒をバランス良く持ったまま片足を前に伸ばし、もう片足を深く曲げるという、見るからにしんどそうなポーズをとります。 そのポーズが決まると、沿道の見物客から歓声と拍手がわき起こります。長い鉾の先には金色の鈴のような飾りが付いていて、動くたびに揺れる音がします。かつて、この鉾を持つ役を経験したという男性によると、「鉾の正式な名称は知らないが、揺れるとポロンポロンと鳴るので、僕たちはこの鉾のことを“ポロンポロン”と呼んでいます」とのこと。 長崎の歴史のよもやま話が集まる長崎歴史文化協会によると、「茂木くんち」に関する詳しい史料は、今のところ確認されていないとか。また鉾の長さは、電線などにひっかかるという事情から、近年1メートルほど短くされたそうです。 鉾持ちの男性が過ぎると、お上りの行列は地域の男たちに担がれた神輿、そして、ハッピ姿の子供たちをのせたペーロン船が続きました。時代の事情による変化を受け入れながら、地道に受け継がれてきた「茂木くんち」。子供たちがお小遣いを片手に出店に急ぐ姿や、沿道でお年寄りが神輿にお賽銭を投げ入れて手を合わせる姿に、ホッと和んだ良いお祭りでした。
もっと読む