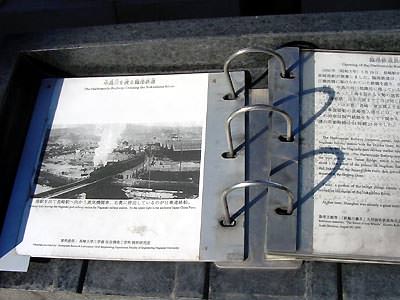第191号【長崎てんぷら】
サク、サクッとした衣に包まれた天ぷら。大好きという人も多いことでしょう。天ぷらはお寿司と並ぶ代表的な日本食のひとつですが、長崎学の書籍などを読むと、織田信長の時代に南蛮人によって長崎に伝えられた料理として紹介されています。最初から日本食だったわけではなかったようですね。 みろくやのホームページに掲載している越中哲也先生の「長崎開港物語~第一回西洋料理編(一)」にも、南蛮料理のひとつとして伝えられたことが記されています。天ぷらという言葉もポルトガル語のTemporaからきたらしいということです。 歴史的に天ぷらにゆかりの深い長崎には、「長崎天ぷら」という郷土料理があります。天ぷらといえば通常、野菜や魚などを、天ぷら粉か小麦粉を水で溶いた衣に包んで油で揚げ、天つゆなどでいただきます。一方、長崎天ぷらは、砂糖や卵であらかじめ味付けした衣で揚げ、天つゆなどは添えないのが特長です。衣の味と食感は、前者があっさり、サクサクとしているのに対し、後者は甘くてサックリ&ポッテリといった感じです。 香ばしく揚がった長崎天ぷらは、揚げ菓子のようでもあり、子供の頃、母親が夕食のおかずにと揚げていくそばから、ひとつ、ふたつ摘んで食べては怒られた記憶があります。我が家では天ぷらといえば、長崎天ぷらがスタンダードで、天つゆでいただく天ぷらは、外食先のものという認識でしたが、周囲10名ほどの友人らの家庭の天ぷらについて聞いてみると、衣に味付けをしない天つゆ派が半分以上という意外な結果が出て驚きました。てっきり、みんな長崎天ぷら派だろうと思っていたからです。 このミニミニ調査の結果では、長崎てんぷら自体を知らない長崎人もいました。また、ふだんは天つゆ派だけど、たまに長崎天ぷらを作るというところもありました。また、長崎天ぷら派の家は、60代以上の家族がいるところばかりでしたので、もしかしたら、あっさり系を好む現代っ子の長崎天ぷら離れという現象が、いつの間にか進行していたのではないだろうかと勝手な想像をします。では、長崎天ぷらの作り方をご紹介しましょう。(1)衣に包む材料を用意します。野菜ならサツマイモ、インゲンマメ、レンコンなど。魚なら甘ダイやブリの切り身やキビナゴなど、お好きなものを選んでください。野菜は適当な大きさに切り、魚類は洗って水気を切り、薄塩をしておきます。(2)衣を作ります。小麦粉1カップと片栗粉小さじ1を合わせて振るい、水50cc、酒大さじ1杯、砂糖大さじ1/2杯、塩少々、卵1個(卵黄のみ1~2個でも可)を加えてよく混ぜ合わせます。調味料の分量などは好みに応じて適宜加減してください。(3)材料の野菜や魚類は水気をとり、衣をつけ油で揚げます。砂糖が入っているので焦げやすくなっていますから火加減に注意して揚げて下さい。さて、長崎天ぷらは、冷めてもおいしいのが特長です。でも、やはり揚げたてがいちばんです。温かいうちに召し上がってください。
もっと読む