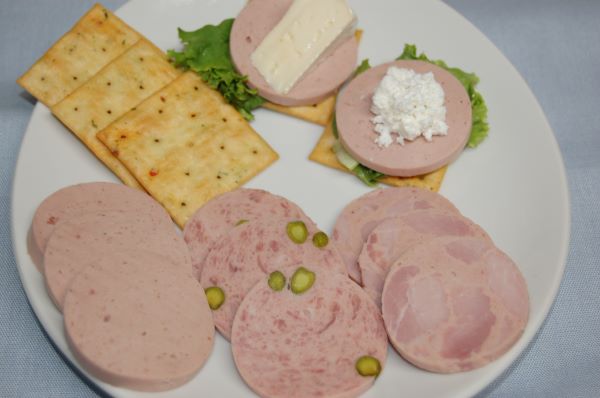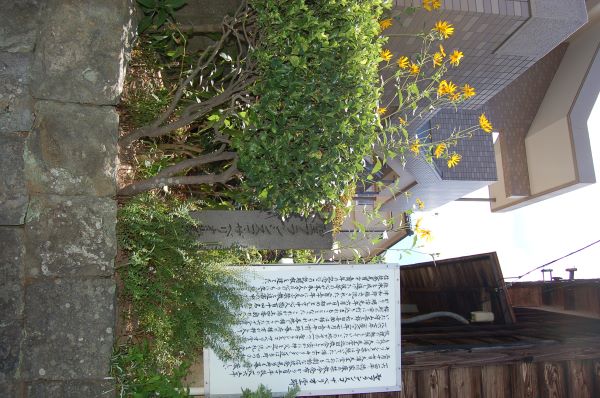第296号【長崎の甘く優しい香り~マダム・バタフライ】
すれちがった人からの香りに、ふと足を止め、思わず振り返る。それは、かつての恋人や気になる人と同じものだったり、懐かしい思い出のシーンの香りだったりして、一瞬にして過ぎ去ったことがよみがえってきます。香りはまるで記憶を呼び覚ます魔法のよう。香りに導かれた思い出にせつなくなったり、やさしい気持ちになったり。この世に香りがなかったら、どんなにつまらないものだったでしょう。 国内外の化粧品メーカーなどからいろいろな種類が出回っている香り。そのタイプも表情も実に多彩です。そんな香水界に、この秋、またひとつ魅力的な香りが誕生しました。その名もオードパルファム『マダム・バタフライ』。長崎を舞台に一途な愛に生きた女性を描いた名作オペラ「マダム・バタフライ」にちなんでつくられた長崎限定の香水です。資生堂と長崎国際観光コンベンション協会の共同開発で、発売から一ヶ月ほどしか経っていませんが、すでにその香りのとりこになってリピータになった女性もいるほど、やさしく素敵な香りです。 長崎港を一望する庭とテラスのある家からストーリーがはじまりまる、オペラ「マダム・バタフライ」は、幕末から明治にかけての物語です。当時の長崎は、開港により多くの外国人がやってきて、街は西洋と東洋がブレンドしたハイカラな空気に包まれていました。そんな時代背景の中、アメリカからやってきた海軍士官ピンカートンと日本人女性の蝶々夫人は出会い、結ばれます。が、やがて夫は本国へ帰ることとなり、彼女は3年以上も待ちわびることに。彼女の心の支えは、夫が別れぎわに残した「バラが咲き、コマドリが巣を作るころ帰ってくる」という約束でした。そして、ようやく長崎にもどってきたピンカートン。しかし、彼は本国で再婚した妻も連れていたのです…。 蝶々夫人の悲恋に多くの人が涙したオペラ「マダム・バタフライ」。そのストーリーの中に、ピンカートンが長崎にくることを知った蝶々夫人が、庭に咲いたバラ、桜、スミレなどたくさんの花々を残らずつんで居間中にまくというシーンがあります。その花々は夫を待つ間、必ず帰ってくると信じて大切に育てていたものでした。ひたむきにひとりの人を思い続けた蝶々夫人。オードパルファム「マダム・バタフライ」は、そんな蝶々夫人の「純愛」をイメージしたのです。 オードパルファム「マダム・バタフライ」の香りは、バラの香りをベースにしたフローラルブーケタイプです。桜や梅などの日本的な香りも配合され、西洋的であり東洋的でもある、まさに長崎らしい香りです。香り立ちは、つけたときから時間の経過によってトップノート(つけてから30分くらい)、ミドルノート(つけてから30分~1時間くらい)、ラストノート(つけてから3時間以上)という3段階に分けられますが、オードパルファム「マダム・バタフライ」の場合、桜・梅・バラの優雅で気品のあるトップノートから、すみれ・ラズベリー・バラのひかえめな甘さに安らぐミドルノート、あやめ・白檀・ホワイトムスクの豊かで温もりのあるラストノートと変化して、つけた人を楽しませてくれます。 ところで、世界中で愛されるバラは、アロマテラピーの世界では、リラクゼーション効果があり、なごやかな気分にしてくれる香りだといわれています。だからなのか、その香りをベースにしたオードパルファム「マダム・バタフライ」をつけると、心地良さに包まれ日常的に愛用したくなります。冬の冷たく乾いた空気の中も、この温かみのある香りがほっと気分をなごませてくれることでしょう。 オードパルファム「マダム・バタフライ」をつけた感想として、「いろんな花の香りが楽しめていい」「どこか懐かしい感じがして好き」「個性が強すぎず、好ましい」「気分が落ち着く」などの声が聞かれました。もうすぐ、クリスマス。バラ好きの女性へ、長崎を懐かしがる方へ、そして自分へ、素敵な香りのプレゼンはいかかですか?記憶に刻まれるロマンチックな香りの思い出が生まれますように。◎参考にした本/ジャコモ・プッチーニ生涯と作品(春秋社)、香水の事典(成美堂出版)
もっと読む