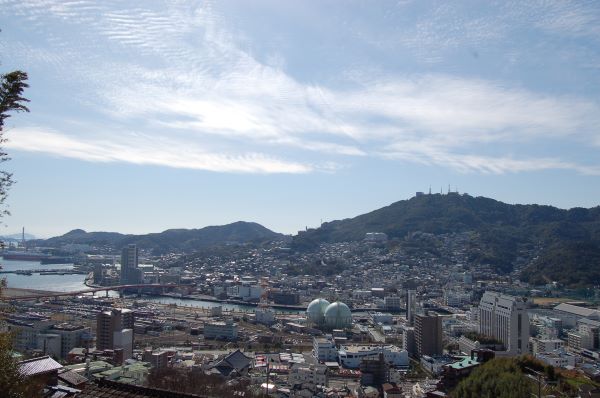第386号【長崎ゆかりのイチジク】
先日の台風12号は大きな爪痕を残しました。被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風シーズンはもうしばらく続きます。それぞれのご家庭で、防災の備えをあらためて確認してみませんか。 さて、日中は残暑が厳しいものの、朝夕に心地よい秋風を感じるようになりました。店頭ではナシやブドウなど旬のくだものがおいしそうに並んでいます。そのなかに赤ワイン色に熟したイチジクの姿を見つけました。 イチジク(クワ科の落葉小高木)の原産はアラビア半島。紀元前3000年頃にはすでに栽培されていたといわれ、聖書ではアダムとイブがイチジクの葉を身に付けたことでも知られています。かなり古くから人間と関わりがあったイチジクですが、日本へ持ち込まれたのは寛永年間の頃(1621~1643)。西南アジアからオランダ船によって長崎に運ばれたのが最初なのだそうです。 ところで、イチジクは「無花果」と書きますが、けして花が無いわけではありません。実の内側にたくさんの花を付け、外側から見えないところから、そう名付けられたようです。あの内側につまった赤いツブツブが実は花だったのですね。 それにしても、中国名の「無花果」と書いて、なぜ「イチジク」と呼ぶのか気になるところです。一説には、一カ月かけて熟すところから「一熟」と呼ばれ、その読みを漢字に当てたのではないかといわれています。また、イチジクは「南蛮柿」、「唐柿」などとも呼ばれるそうで、もしかしたらオランダ船だけでなく、唐船も運んで来ていたのかもしれません。 「不老長寿のくだもの」といわれるほど栄養価が高く薬効もあるイチジク。葉や実は、日本に渡ってきたときから薬として用いられていました。たとえば、便秘をはじめ喉の痛みなどの炎症を抑えるなどの効果があり、お酒を飲んだあとに食べると二日酔いの予防にもなるそうです。いまは乾燥させたものが一年中手に入りますが、生のものは日持ちがしないので、多めに手に入ったらジャムにするといいかもしれません。 ところで「不老長寿のくだもの」というと、「ザクロ」もそうです。実の内側にたくさんつまった種子の様子はイチジクにも少し似ています。独特の酸味と甘味がある、ちょっと高価な果実です。長崎くんちの踊り町が10月3日に行う「庭見世」の際、縁起のよい秋の味覚のひとつとして豪華に飾られます。ザクロを使ったナマスもくんち料理のひとつとして親しまれています。 長崎ゆかりのイチジク、そしてザクロ。旬のおいしさを味わってみませんか。 ◎参考にした資料/「生活情報シリーズ⑨くだものの知識」(国際出版研究所 発行)、「からだによく効く食べ物事典」(三浦理代 監修)、「ながさきことはじめ」(長崎文献社 編)
もっと読む