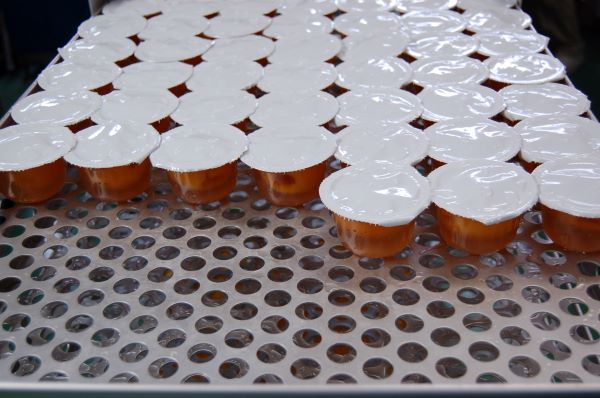第311号【長崎半島の海水浴場を訪ねて】
夏といえば、海水浴。テレビゲームがなかった時代、海辺の小さな漁村で育った友人は、毎日のように素潜りを楽しみ、友だちと泳ぎまくっていたそうです。大人になって都会で暮らすようになると、海はいつの間にか遠い存在に。潮の匂い、海底の美しい砂模様、海中で出合った魚たち。今も忘れられない子供の頃の海体験は、大切な宝物だと話してくれました。 きれいな海に囲まれた長崎は、海水浴場も近場にいっぱい。長崎駅のある市中心部から車で30~60分であちこちに点在するお気に入りのビーチへ行くことができます。今回はその中から九州本土西南端に位置する長崎半島(野母半島)の海水浴場をご紹介します。 長崎半島は、長崎市街地から南西に伸びた半島で、緑豊かな山が連なり、周囲は五島灘、東シナ海、橘湾、天草灘と美しい海に囲まれています。長崎半島の先端にあたる地域は「野母崎」と呼ばれ、対馬暖流の影響もあって、気候は年間平均気温18度の温かさです。道路を走る車両の数は少なく、あたりは鳥の鳴き声や波音に包まれています。ここに、「脇岬(わきみさき)海水浴場」という長崎県でも最南端に位置するビーチがあります。周囲には、ハマユウが自生、さらにヤシ類など亜熱帯植物も植栽されていて、南の島のような雰囲気が漂っています。 「脇岬海水浴場」は、1、3キロメートルも続く白砂のビーチ。環境省が水質が良好で快適な水浴場として選定した「日本の水浴場88選」にも選ばれています。毎年、夏休みになると家族連れや若者たちを中心とした海水浴客で大賑わい。波がいいらしく、夏場以外でもサーファーたちの姿が見られます。波打ち際を歩けば、小さな貝殻やきれいな石ころがいっぱい。お気に入りの貝殻を集めて、名前を調べれば、夏休みの作品が一丁あがりです。 「脇岬海水浴場」から背後の山間へ向かって5分ほど歩くと、石崎融思や川原慶賀らが描いたとされる天井絵などで知られる観音寺があります。和銅2年(709)に開かれたという由緒あるお寺で、江戸時代には、「みさき道」と呼ばれる長崎から半島の先端にあるこの地までの道を通って、多くの人々が参拝に訪れたといいます。その昔、中国船が長崎へ入港する際、風待ち港として利用したといわれるこの地の港。このお寺で、航海の安全が祈願されたようです。 「脇岬海水浴場」から海岸沿いの道路を10数分ほど北上したところに、小さい子供連れの家族に人気の「高浜海水浴場」があります。延長約800メートル、波静かな遠浅の美しいビーチで、「日本の渚百選」、「日本の水浴場88選」、「快水浴場百選」に選ばれています。沖合いには真正面に端島(軍艦島)を望み、その光景を見るためにわざわざ訪れる観光客もいます。 「高浜海水浴場」の海水は、透明度が高くて本当にきれいです。聞くところによると、ウミガメの産卵もみられるそうです。この海水浴場も「脇岬海水浴場」と同じく、背後に緑の山が控えていました。山が豊かだと、海も美しいということを実感できます。ここで桟敷きを営業している方が、背後の山のひとつを指差して、「あれが、殿隠山(とのがくれやま)ですよ。歴史好きの人たちがときどき来てるみたい」と教えてくれました。ここ高浜地区には、鎌倉時代、関東から下向してきた深堀氏にゆかりの正瑞寺があり、「そのお寺に地蔵菩薩像という有名なお地蔵さんが安置されているんですよ」とのこと。どうやら、この界隈、興味深い歴史がいろいろありそうです。海水浴シーズンが終わったら、ゆっくり訪ねたいと思います。
もっと読む