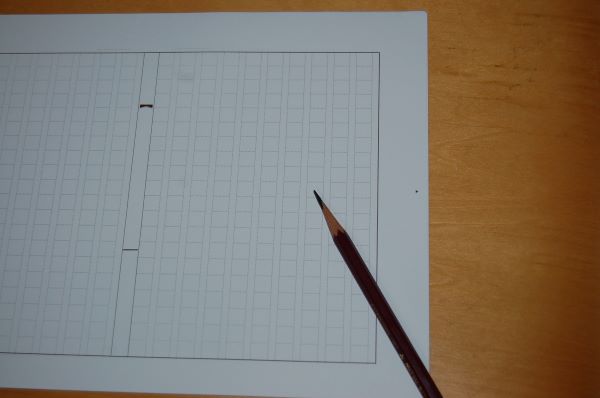第431号【近代通信網のはじまり(郵便・電信)】
長崎の路地裏を歩いていると、昭和の雰囲気を残す丸型ポストを見かけることがあります。鉄製のこのタイプは、戦後、物資が行き渡りはじめた頃の昭和24年から実用化されたもの。戦後の復興から現在に至るまで情報伝達の役割を果たしながら、ずっと私たちの暮らしを見守ってきたのですね。 ポストといえば、ちょっと珍しいタイプが長崎県庁そば(長崎市江戸町)に設置されています。「黒ポスト」と呼ばれる角柱型の郵便箱で、明治期に使用されたデザインを復元したもの。通常のポストと同様に利用されています。 日本の郵便制度が生まれたのは、明治4年(1871)3月1日(新暦4月20日)。まず東京 ・京都・大阪の3都市に現在の郵便局を意味する「郵便役所」と、その間を結ぶ東海道筋の各宿駅に「郵便取扱所(62カ所)」を設けスタートしました。同年12月には九州で最初の「郵便役所」が長崎につくられ、東京~長崎間の郵便線路が開通。このとき長崎~小倉を結ぶ長崎街道沿いに「郵便取扱所(16カ所)」が設けられ、郵便ネットワークは九州全域へと広がっていきました。 東京~長崎間の郵便線路は、東海道、山陽道、西海道の各宿駅を継ぎ渡していくもので、それまでの飛脚による所要時間が190時間ほどかかっていたのが、半分の95時間に短縮されたそうです。現在、「長崎郵便役所」があった場所(長崎市興善町)には、「長崎東京間郵便線路開通起点の跡」の碑が建てられています。 一方、電信の分野では、郵便制度スタートの同年にデンマーク系の大北電信会社が、長崎~上海間と長崎~ウラジオストック間に海底電線を開通させました。当時、世界の通信網のトレンドは海底電線で、その敷設によって世界をひとつにつなげようとしていたのです。さらに当時の先進諸国は、日本国内における海底電線敷設権をめぐって競争を展開。明治政府は、通信主権を守るため、自らの手で国内電信線の架設を試み、技術的にはイギリスの力を借りながらも郵便線路開設から2年後の明治6年に、東京~長崎間の電線を架設。東京から長崎・上海経由で、ヨーロッパ諸国へ電信を交わせるようになりました。 現在、グラバー園(長崎市南山手)へ向かう坂の登り口に、「長崎電信創業の地」「国際電信発祥の地」という2つの碑が建っています。当時、ここにあったベルビューホテルの一角に大北電信社の通信所が設けられ、世界との交信が行われたのです。 江戸時代、主に出島を通じて西欧諸国の情報を入手していた日本。明治という新しい時代にとって、郵便線路や電信など情報・通信網の整備は、近代国家を築くうえで不可欠な課題でした。長崎はそうした動きの重要な拠点のひとつだったのです。 ●参考/『日本郵便創業の歴史』(藪内吉彦)
もっと読む