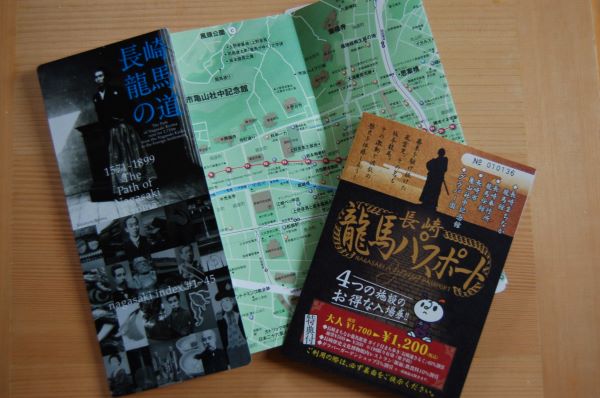第356号【長崎の津々浦々~浦上川~】
梅雨入り直前。晴天が続くいまのうちにと、衣更えやカーテン、じゅうたんなどの洗濯、押し入れの片付けなど、家中の整理整頓や掃除にいそしんでいる方も多いことでしょう。風薫るこの季節は、まち歩きにも最適なシーズンです。今回も外へ出て長崎市の浦上川沿いをのんびり歩いてきました。 長崎市の北東部の山を水源とする浦上川は、市街地の中を流れ、長崎港へ注ぐ川。眼鏡橋などの石橋群が架かる中島川とともに、長崎市を代表する河川です。散策のスタートは、浦上地区界隈にある「長崎県営野球場ビッグNスタジアム」前です。浦上川の下流に位置するここから、めざす河口の長崎港まで約3km。この間に架かっている橋は、上流から下大橋(しもおおはし)、簗橋(やなばし)、竹岩橋(たけいわばし)、梁川橋(やながわばし)、稲佐橋(いなさばし)、旭大橋(あさひおおはし)など。河口までは、川の両サイド、もしくは片側に歩道が整備されているので、車両の往来をあまり気にせずズンズン歩いていけます。 スタート地点の少し上流には「大橋(おおはし)」が架かっています。その辺りまではたくさんのコイが泳ぎ、サギ類やマガモなど野鳥の姿もいろいろ見られるのですが、その数十メートル下流で、かすかに潮の香りが漂いはじめる「下大橋」辺りになると、そうした生き物の姿がぐん減るようです。今回、アオサギを数羽確認しただけでした。 浦上地区界隈の流域は、野球場をはじめプール、陸上競技場、ラグビー・サッカー場などがあるスポーツエリアです。高総体を目前に控えた時期ということもあり、日焼けした高校生たちが行き交っていました。彼らのまぶしい姿を見て、あらためて思ったのは平和の尊さです。 65年前の8月9日。浦上地区に投下された原子爆弾で、この界隈は一瞬にして焼け野原と化し、浦上川では、水を求めて集まった大勢の被爆者が息絶えました。その悲惨な光景を目の当たりにした知人(70代)は、「この流域は、私にとって聖地なんです」といいます。それは、原子爆弾の悲惨さを知るみんなの思い。毎年8月9日の夜には、陸上競技場近くに架かる簗橋付近では、犠牲者の霊をなぐさめ、平和を祈る「万灯流し」が行われています。 川沿いを下っていくと、梁川橋のかかる茂里町あたりから浦上川沿いに、都市計画道路の「浦上川線」が建設中(今年度完成予定)でした。梁川橋から稲佐橋まで続く歩道には、関山桜、うこん桜、蘭々桜といったいろいろな種類の桜の木が植えられていました。満開の季節にもぜひ、訪れたいものです。 稲佐橋から河口にかかる旭大橋付近になると、川面はもうすっかり海の色。数羽のミサゴが飛び交い、小さな波がチャプチャプと音を立てていました。右手を見上げればロープウェイのある稲佐山、左手の向こう側には彦山が見えます。旭大橋の下をくぐると、近年の開発で大きく変化した長崎港の景色が広がりました。港では、ゆったりと流れる長崎の時間の中で、羽をのばす修学旅行生の姿がありました。
もっと読む