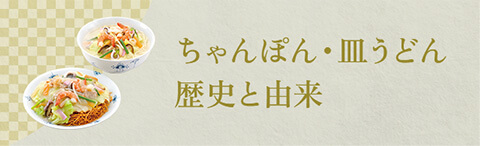第673号【節分と長崎ランタンフェスティバル】
2月3日節分の日の夕刻、役目を終えた正月飾りやお札を持って、諏訪神社(長崎市上西山)へ。すでに大きな炎を上げていた鬼火焚きの中へ投げ入れ、炎にあたりながら無病息災と家内安全を祈願しました。そのあと、徒歩圏内に点在する松森神社、桜馬場天満神社、伊勢宮神社、宮地嶽八幡神社、そして興福寺にも足を運び、それぞれの節分行事の様子を見て回りました。 真冬の夜にも関わらず、どこも境内を埋め尽くすほどの人出。鬼火焚きのかたわらで、年男・年女による豆まきや、ぜんざいなどの温かいものも振る舞われ、なごやかな雰囲気が漂っていました。世代を問わず、大勢の人々が繰り出す節分の行事ですが、翌朝には何事もなかったようになるから不思議です。この伝統行事はこれからも脈々と受け継がれていくのでしょう。 この冬は、連日の北国の大雪のニュースに心が痛みます。一方、九州は、時折強い寒波が到来するものの、雪や雨が少なく乾燥した状態が続いています。今月最初の日曜日、今季最強の寒波が訪れましたが、長崎では、平地にうっすらと雪が積もる程度でした。その日、小雪が舞うなか背中を丸めて中島川沿いを歩いていたら、川石の上からじっと水面をにらむカワセミを見かけました。まん丸に羽毛を膨らませた姿がかわいい。どうやら、稚魚を狙っているようです。野鳥って、本当にたくましいですね。 さて、長崎はいま「2026長崎ランタンフェスティバル」を開催中(2/6〜2/23迄)です。長崎市内の中心部に、約1万5千個に及ぶランタンやオブジェが飾られ、夕刻になると極彩色の幻想的な灯りで彩られます。 長崎の冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」は、これまで、旧暦の元旦から開催されていましたが、旧暦元旦は、西暦にすると1月下旬から2月の間で年ごとに変わるため、今年から2月の第1金曜日から17日間の開催に固定化されることになりました。(今年は、最終日の翌日が祝日になるため1日延長して18日間の開催。)この期間なら、春節(旧暦の正月期間)と重なる日もあるので、これまでどおり、旧暦新年を祝うことができますね。 新地中華街会場の湊公園には、大きな干支のオブジェ『龍馬精神(りょうませいしん)』がお目見え。龍のように天を駆け、馬のように地を駆ける、若々しく活気に満ちた精神が表現されています。『龍馬精神』という言葉は、健康や活力願うときにも使われるそうです。ランタンフェスティバル開催期間中の平日には、市中心部に設けられた複数の会場で、龍踊りや二胡演奏、中国変面ショー、土曜日には「皇帝パレード」、日曜日には「媽祖行列」とさまざまな催しが展開。毎日、見どころ満載です。 道なりに、どこまでも連なるランタンは、まるで龍のよう。空中を縦横無尽に泳いで、ランタンのまちを楽しんでいるかのようです。あなたも、さっそく、お出かけになりませんか。
もっと読む